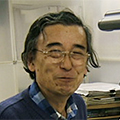温泉は不変、時代は変遷、価値観は変化。
次代の湯治宿は何か、湯治場はどう生きるか。
明治後期、二代目・志乃の夢枕にお告げがあり温泉が湧出し、
同四十三年に創館と伝えられる東鳴子温泉の旅館大沼。
百余年に渡り、快浴洗心・湯食同泉の場として、湯治の時空間
をつなぎ伝える宿が、このたび改修いたします。
風の又三郎のような六代目を膝に、ひと月も閉館して大改修に
踏み切った五代目湯守は、笑っていいます。
どこを改修したか分からないでしょうね。
湯治場の最大の馳走は湯。その湯を、たゆとうと、七つの内湯、
一つの離れ湯に、源泉かけ流しで朝から晩まで満たすべく、費
用の殆どは配管交換となるのです。
今度は、八つの内湯ですよ。
いたずら笑いの目線の先は、いま座っているロビーのソファへ。
坐り湯治!その生地は、地名由来の赤湯に倣って美麗なレッド。
昔から海彦山彦の交流がある塩竈。その神社御門前にアトリエ
構えた若手椅子職人が張り替えたソファは、尻が離さない心地
佳さです。
湯治スイートなる続きの間や、湯あがりにクールダウンしてくれる
ブルーベリーの鳴子キールなど、遊び心でリノベーションの由。
湯は癒で悠、そして愉で遊。総じて、ゆ。
湯治の原点に立ち返り、しかし今の時代の新しい感性と出会って、
またゆっくり次の百年を歩んでいく"ゆ宿"に、拍手。
※はなれ山荘 庭園露天「母里の湯」。雨の風情はひとしおです。
四方山雑記帳
東北・宮城・仙台マーケットの小ネタ小ばなし